2020年4月15日号
毎年恒例の「冬の参与会」が,1月25 日(土)京都ブライトンホテルにおいて開催され,参与24 名,府医から27 名が出席した。
府医からのテーマとして「医師確保計画中間案」,「これからの医療を考えるためのアンケートの集計結果」,「新型コロナウイルス」について報告を行った後, 船井医師会から「府医における児童虐待への対応」について意見・要望が出され, 約2時間にわたり活発な意見交換が行われた。

近年,医師数は増加傾向にあるものの,過疎地域から都市部への偏在拡大が見受けられるだけでなく,外科や産婦人科など一部の診療科の医師数は減少傾向にある。
昨年4月1日の改正医療法・医師法施行にともない,都道府県は医師偏在対策に取組むための「医師確保計画」を令和元年度内に策定することが求められている。
法改正の趣旨は,「地域間の医師偏在の解消等を通じ,地域における医療提供体制を確保するため,都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定,臨床研修病院の決定権限および研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる」こととされている。
次に,地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応については,「外来医療機能に関する情報の可視化」,「新規開業者等への情報提供」,「外来医療に関する協議の場の設置」の3点が求められており,その協議の場として,地域医療構想調整会議が例示されている。
府医および参与からの意見は下記のとおり。
〈府医〉
〈参与〉


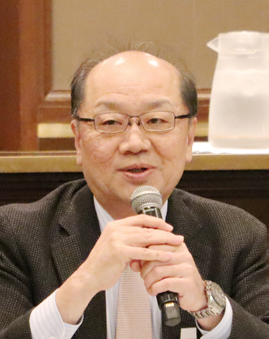
各医療圏における医療提供体制の実情を把握し,地域医療構想調整会議での協議における参考データとすることを目的に診療所A会員(1,964 人)を対象として「これからの医療を考えるためのアンケート」を実施(回答率:25.2%)。
集計結果から,75 歳以上の外来通院中または訪問診療中の患者に入院が必要となった場合の病院の受け入れ状況については同じ医療圏でも,疾患によって相違があった。
特に,「がん患者の苦痛の増強」,「認知症患者の身体合併症」,「認知症患者のBPSD 増悪」において受け入れ先の確保に苦労している傾向が見られた。
アンケートの自由記載欄では,丹後ブロックから高齢者の数に大きな変化はないものの総人口は3割以上減少しており,働き手の確保が困難になるとの記載があり,このような地域でしか分からないデータを基に検討する必要があるとの考えを示した。

中国では1月25 日時点で患者1,287 人, 死者41 人まで感染が拡大している。コロナウイルスは大変変異しやすいウイルスであり,SARS やMERS もコロナウイルスの一種で,新型も変異し,重篤化すれば, 行政として緊急的に様々な対応が必要になるとした。現在,国内でも3例報告されているが,重篤ではなく治癒された方もいると聞き及んでいる。人から人による飛沫感染が最も深刻な感染原因となっており,1月24 日には「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議」も開催され,国を挙げて対策に取組んでいるところである。
中国あるいは武漢市からの渡航者が,医療機関を受診された場合に,基本的に入院が必要なものについては,感染症指定医療機関での入院となる。行政としては土曜日・日曜日でも緊急的に感染症指定医療機関と連絡を取れるように連携しているとし,疑い例があれば各保健所に連絡するよう求めた。また,医療機関に対しアルコール消毒の徹底や手袋・マスクの装着を促すよう協力を求めた。
新型コロナウイルスの検体検査は国立感染症研究所のみであるが,同研究所で簡易検査キットを開発中であると付け加えた。
万一の事態に備え,行政機関とより一層の連携を図るべく,地区感染症対策担当者連絡協議会を2月6日(木)午後2時30 分より開催することを報告。
また,日々データが更新されるため,府医会員ML・FAX 情報に注意するよう呼びかけたものの, 参与からは,府医からの広報協力要請が多すぎることと,テレビでの報道の方が先なので会員は情報を得ていると思うが,どれを優先的に広報すべきか判断が難しいと意見が出された。京都府からは,主に医療機関での対応が最重要であるため, 国立感染症研究所が発出している院内感染対策の通知を優先的に広報するよう求めた。
現在,すべての地区医が代表者会議には参画しているものの,実務者会議および個別ケース会議への参画は中丹地区のみである。
参与からの意見は下記のとおり。
府医としては,「京都市要保護児童対策地域協議会」に参画している。
京都市では,平成24 年度より体制が変わり,「京都市児童相談所」,「京都市第二児童相談所」の二ヶ所で対応している。
個別ケースについては医師会に連絡はなく,各地区による対応差があることも考えられるので, 現在,乳幼児保健委員会で要保護児童虐待に対する対応を各地区でどの程度できるのかについてアンケート調査を準備しているとし,各地区での結果を見て,関係諸団体と協議の上,積極的に取組んでいきたいと説明。また,月1回での会議に参加することは負担となるため,テレビ会議などICT を活用した会議やリアルタイムの情報連携について行政に申し入れしていきたいと付け加えた。