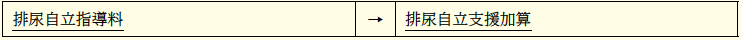厚生労働省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたのでお知らせします。
なお,本内容については,日医ホームページ,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和2年3月5日保医発0305 第1号)
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
第1部 初・再診料
第1節 初診料
A000 初診料
⑻ 許可病床の数が400 床以上の病院(特定機能病院,
許可病床の数が400 床以上の 地域医療支
援病院及び一般病床の数が200 床未満の病院を除く。)のうち,前年度1年間の紹介率の実績
が40%未満かつ逆紹介率の実績が30%未満の保険医療機関の取扱いについては,⑺と同様で
あること。
第2節 再診料
A003 オンライン診療料
⑺ オンライン診療を行う医師は,オンライン診療料の対象
となる管理料等を算定する際に診療
を行った医師,
在宅自己注射指導管理料を算定する際に診療を行った医師又は頭痛患者に対す
る対面診療を行った医師と同一のものに限る。
⒁ オンライン診療料を算定する場合は,診療報酬明細書の摘要欄に,該当するオンライン診療
料の対象となる管理料等の名称及び算定を開始した年月日
在宅自己注射指導管理料の算定を又は頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日を記載すること。
第2部 入院料等
第2節 入院基本料等加算
A205 救急医療管理加算
⑶ 救急医療管理加算2の対象となる患者は,⑵のアからケまでに準ずる状態又はコの状態に
あって,医師が診察等の結果,緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお,当該
加算は,患者が入院時において当該
重症患者の状態であれば算定できるものであり,当該加算
の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。
A250 薬剤総合評価調整加算
⑴ 「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算は,複数の
内服薬薬剤が処方されている患者であっ
て,薬物有害事象の存在や服薬過誤,服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して,
処方の内容を総合的に評価した上で,当該処方の内容を変更し,当該患者に対して療養上必要
な指導を行う取組を評価したものであり,次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定す
る。
ア (略)
イ アを踏まえ,患者の病状,副作用,療養上の問題点の有無を評価するために,医師,薬剤
師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し,薬剤の総合的な評価を行い,適切
な
用法及び用量への変更,副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また,評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ (略)
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無
について,多職種で確認し,必要に応じ
て,再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
⑼ 「注2」に規定する薬剤調整加算は,「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要
件を満たした上で,薬効の重複する薬剤の減少
又は合剤への変更等により,退院時に処方され
る内服薬が減少したことを評価したものである。
第3節 特定入院料
A303 総合周産期特定集中治療室管理料
⑸ 「1」の母体・胎児集中治療室管理料を算定する場合は,
⑵のアからカまでのいずれに該当
するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。「2」の新生児集中治療室管理料を算定す
る場合は,区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の⑴のアからスまでのいずれに該
当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
⑵ 新生児治療回復室入院医療管理料の算定対象となる新生児は,次に掲げる状態にあって,
医
師保険医が入院医療管理が必要であると認めた者である。
アからス(略)
A311 精神科救急入院料
⑶ ⑴のウに該当する患者については,当該保険医療機関の他の病棟から転棟後,当該病棟にお
いてクロザピンの投与を開始した日から起算して3月を限度として算定する。ただし,クロザ
ピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
ア
クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由により,
投与を中止した場合は,投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる。
イ
ア以外の患者事由により,投与を中止した場合は,投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。
⒅ ⑴のウに該当する患者について,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。また,当該病棟において,クロザピンの投与を中止した場
合は,投与中止日及び投与を中止した理由を⑶のア又はイのいずれか該当するものを診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。あわせて,同一の保険医療機関において,⑴のウに該当する
患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場合は,転棟す
る以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与中止回数を診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。なお,通算の投与中止回数に⑶のア又はイのいずれかに該当するも
のとして中止した場合は含めないこと。
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
⑷ ⑴のウに該当する患者については,当該保険医療機関の他の病棟から転棟後,当該病棟にお
いてクロザピンの投与を開始した日から起算して3月を限度として算定する。ただし,クロザ
ピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
ア
クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由により,
投与を中止した場合は,投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる。
イ
ア以外の患者事由により,投与を中止した場合は,投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。
⑾ ⑴のウに該当する患者について,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。また,当該病棟において,クロザピンの投与を中止した場
合は,投与中止日及び投与を中止した理由を⑷のア又はイのいずれか該当するものを診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。あわせて,同一の保険医療機関において,⑴のウに該当する
患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場合は,転棟する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与中止回数を診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。なお,通算の投与中止回数に⑷のア又はイのいずれかに該当するも
のとして中止した場合は含めないこと。
A311-3 精神科救急・合併症入院料
⑶ ⑴の
エウに該当する患者については,当該保険医療機関の他の病棟から転棟後,当該病棟に
おいてクロザピンの投与を開始した日から起算して3月を限度として算定する。ただし,クロ
ザピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
ア
クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由により,
投与を中止した場合は,投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる。
イ
ア以外の患者事由により,投与を中止した場合は,投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。
⑿ ⑴のエに該当する患者について,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。また,当該病棟において,クロザピンの投与を中止した場
合は,投与中止日及び投与を中止した理由を⑶のア又はイのいずれか該当するものを診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。あわせて,同一の保険医療機関において,⑴のエに該当する
患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場合は,転棟す
る以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与中止回数を診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。なお,通算の投与中止回数に⑶のア又はイのいずれかに該当するも
のとして中止した場合は含めないこと。
第1部 医学管理等
B005-1-2 介護支援等連携指導料
⑻ 当該共同指導は,当該患者が入院している保険医療機関の医療関係職種と介護支援専門員又
は相談支援専門員が,患者が入院している保険医療機関において実施することが原則であるが,
ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
この場合において,
患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は,患者の同意を得ていること。また,
保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末におい
て共同指導を実施する場合には,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」に対応していること。
B013 療養費同意書交付料
⑴ 療養費同意書交付料は,
当該疾病について現に診察している原則として当該疾病に係る主治
の医師
(緊急その他やむを得ない場合は主治の医師に限らない。)が,
当該診察に基づき,
⑵
から⑷までの療養費の支給対象に該当する療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に
対し,あん摩・マッサージ・指圧,はり,きゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意
書等」という。)を交付した場合に算定する。
⑸
(患者が同意書等により療養費の支給可能な期間(初療
又は同意の日から
6月。
3月(変形徒
手矯正術に係るものについては1月)を
超えて経過してさらにこれらの施術を受ける必要があ
る場合において,
医師が当該患者に対し同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。た
だし,同意書等によらず,医師の同意によった場合には算定できない。
⑹ 同意書等を再度交付する場合,前回の交付年月日が月の15 日以前の場合は当該月の4ヶ月
後の月の末日,月の16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算
定できない。ただし,変形徒手矯正術については,前回の交付年月日から起算して1ヶ月以内
の交付については1回に限り算定できる。
(
76) 医師が同意書等を交付した後に,被保険者等が当該同意書等を紛失し,再度医師が同意書
等を交付した場合は,最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において,2
度目の同意書等の交付に要する費用は,被保険者の負担とする。
第2部 在宅医療
第2節 在宅療養指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C152-2 持続血糖測定器加算
⑴ 入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に対して,持続的に測定した血糖値に基づく
指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。
ア (略)
イ 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 急性発症若しくは劇症1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって,皮下インスリン注
入療法を行っている者。
ロ 内因性インスリン分泌の欠乏(空腹時血清Cペプチドが0.5
nmg/ml 未満を示すものに
限る。)を認め,低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロール
が不安定な2型糖尿病患者であって,医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のあ
る,皮下インスリン注入療法を行っている者。
⑺ 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合には,次のいずれも満た
す場合に算定できる。
ア・イ (略)
ウ 次のいずれかに掲げる者が,患者又は患者家族等に対し,持続血糖測定器の使用方法の十
分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖及び高血糖への対応等,必要な指導を行っ
ていること。
イ 糖尿病の治療に関し,専門の知識及び5年以上の経験を有
し,持続血糖測定器に係る適
切な研修を修了したする常勤の医師。
ロ 糖尿病の治療に関し,治療持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し,
持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師。
なお,ここでいう
適切な研修とは,次の事項に該当する研修のことをいう。
エ ウのイ及びロに掲げる適切な研修とは,次の事項に該当する研修のことをいう。
イ① 医療関係団体が主催する研修であること。
ロ② 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識,評価方法,セルフケア支援,持続血
糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。
第3節 薬剤料
C200 薬剤
⑵ 上記の注射薬の投与日数は,以下のとおりである。
ア・イ(略)
ウ 30 日分を限度に投与することができるもの
ブプレノルフィン製剤,モルヒネ塩酸塩製剤,フェンタニルクエン酸塩製剤,
ヒドロモル
フォン塩酸塩製剤
第3部 検査
第1節 検体検査料
第1款 検体検査実施料
D004-2 悪性腫瘍組織検査
⑸ 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して「1」の「イ」処理が容易なも
のと「1」の「ロ」処理が複雑なものを実施した場合は,
「注1」及び「注2」の規定に基づき,
それぞれの検査の項目数に応じた点数所定点数を合算した点数により算定する。
D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)
⑴ 血液粘弾性検査は,
心臓血管手術開心術(人工心肺を用いたものに限る。)を行う患者に対
して,血液製剤等の投与の必要性の判断又は血液製剤等の投与後の評価を目的として行った場合に算定できる。
D023 微生物核酸同定・定量検査
⒄ SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう。以下同じ。)核酸検出は,喀痰,気道吸引
液,肺胞洗浄液,咽頭拭い液,鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を用いて,国立感染症
研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに
準じたもの又は体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV- 2の検出
(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより,
COVID-19(新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者であることが疑われる者
に対しCOVID-19 の診断を目的として行った場合又はCOVID-19 の治療を目的として入院
している者に対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合に限り算定できる。ただ
し,感染症の発生の状況,動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実
施した場合は算定できない。
採取した検体を,国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス
2013-2014 版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って,検体採取を行った
保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は,本区分の「
1412」SARS コ
ロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定し,それ以外の場合は,
同点数3回分を合算した点数を準用して算定する。なお,
採取した検体を,検体採取を行った
保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は,検査を実施した施設名を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し,診断を目的として本検査を実施した場
合は,診断の確定までの間に,上記のように合算した点数を1回に限り算定する。ただし,発
症後,本検査の結果が陰性であったものの,COVID-19 以外の診断がつか
ず,本検査を再度
実施した場合は,ない場合は,上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。な
お,本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し,退院可能かどうかの判断を目的と
して実施した場合は,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新
型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年2
月18 日健感発0218 第3号)の「第1 退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り,
1回の検査
につき上記のように合算した点数を算定する。なお,検査を実施した日時及びその
結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
第3節 生体検査料
D285 認知機能検査その他の心理検査
⑸ 区分番号「D283」発達及び知能検査の「2」とは,MCC ベビーテスト,PBT ピクチュア・ブロッ
ク知能検査,新版K式発達検査,WPPSI 知能診断検査,
WPPSI-Ⅲ知能診断検査,全訂版
田中ビネー知能検査,田中ビネー知能検査Ⅴ,鈴木ビネー式知能検査,WISC-R知能検査,
WAIS-R成人知能検査(WAIS を含む。),大脇式盲人用知能検査,ベイリー発達検査及び
Vineland-Ⅱ日本版のことをいう。
⑽ 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」の簡易なものとは,
MAS 不安尺度,MEDE 多面的初期認知症判定検査,AQ 日本語版,日本語版LSAS-J,M
-CHAT,長谷川式知能評価スケール及びMMSE のことをいい,「ロ」のその他のものとは,
CAS 不安測定検査,SDS うつ性自己評価尺度,(中略)SIB,Coghealth(医師,看護師又は
公認心理師臨床心理技術者が検査に立ち会った場合に限る。),NPI,BEHAVE-AD,(以下略)
⒂ 平成31 年4月1日から当分の間,以下のいずれかの要件に該当する者は,公認心理師とみ
なす。
ア 平成31 年3月31 日時点で,臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
第8部 精神科専門療法
第1節 精神科専門療法料
I002 通院・在宅精神療法
「注8」に規定する療養生活環境整備指導加算は,通院・在宅精神療法の「1」を算定する
患者について,
精神病棟当該保険医療機関における直近の入院において,区分番号「B015」
精神科退院時共同指導料の「1」精神科退院時共同指導料1を算定した患者であって,退院し
た日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診したもの又はその家族等に対して,
精神科を担当する医師の指示の下,保健師,看護師又は精神保健福祉士が,療養生活環境を整
備するための指導を行った場合に月1回に限り算定できる。(以下略)
I016 精神科在宅患者支援管理料
⒃ 令和2年3月31 日時点で,現に精神科在宅患者支援管理料「1」のハを算定している患者
については,令和3年3月31 日までの間に限り,引き続き算定できる。
第9部 処置
J038-2 持続緩徐式血液濾過
⑵ 持続緩徐式血液濾過は,次のアからケまでに掲げるいずれかの状態の患者に算定できる。た
だし,キ及びクの場合にあっては一連につき概ね8回を限度とし,ケの場合にあっては一連に
つき月10 回を限度として3月間に限って算定する。
ア・イ(略)
ウ
急性腎障害と診断された薬物中毒の患者
エからケまで(略)
J039 血漿交換療法
⒄ 当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症については,次のいずれかに該当する者
のうち,黄色腫を伴い,負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であり,
維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。
ア 空腹時定常状態の血清LDL コレステロール値が370mg/dL を超えるホモ接合体の者
イ
食事療法及び薬物療法を行っても血清LDL コレステロール値が170mg/dL 以下に下がら
ないヘテロ接合体の者
第10 部 手術
第1節 手術料
第2款 筋骨格系・四肢・体幹
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
手指又は足趾の切断術を行った場合は,区分番号「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟
部形成のみのもの)指(手,足)又は区分番号「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形
成を要するもの)指(手,足)のいずれかの所定点数により算定する。
K087 断端形成術(骨形成を要するもの)
手指又は足趾の切断術を行った場合は,区分番号「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟
部形成のみのもの)指(手,足)又は区分番号「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形
成を要するもの)指(手,足)のいずれかの所定点数により算定する。
第8款 心・脈管
K546 経皮的冠動脈形成術
⑴
一方向から造影して区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄
病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお,医学的根拠に基づきこ
れ以外の症例に対して算定する場合にあっては,診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学
的根拠を詳細に記載すること。
K547 経皮的冠動脈粥腫切除術
⑴
一方向から造影して区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄
病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお,医学的根拠に基づきこ
れ以外の症例に対して算定する場合にあっては,診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学
的根拠を詳細に記載すること。
K549 経皮的冠動脈ステント留置術
⑴
一方向から造影して区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄
病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお,医学的根拠に基づきこ
れ以外の症例に対して算定する場合にあっては,診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学
的根拠を詳細に記載すること。
第9款 腹部
K716 小腸切除術
「1」については,クローン病の患者のうち,複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるもの
又は悪
性腫瘍に対して小腸切除術を実施した場合は,本区分の所定点数により算定する。
K716-2 腹腔鏡下小腸切除術
「1」については,クローン病の患者のうち,複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるもの
又は悪
性腫瘍に対して小腸切除術を実施した場合は,本区分の所定点数により算定する。
K726 人工肛門造設術
区分番号「K740」直腸切除・切除術の「
54」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の
切除等の手技料は,それぞれの所定点数に含まれ,別に算定できない。
K732 人工肛門閉鎖術
「2」の「イ」直腸切除術後のものについては,悪性腫瘍に対する直腸切除術
(ハルトマン手術)
の際に造設した人工肛門に対して,人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。
第10 款 尿路系・副腎
K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
⑴ 過活動
性膀胱又は神経因性
膀胱排尿筋過活動の患者であって,行動療法,各種抗コリン薬及
びβ3作動薬を含む薬物療法を単独又は併用療法として,少なくとも12 週間の継続治療を行っ
ても効果が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り,算定
できる。
第3節 手術医療機器等加算
K936 自動縫合器加算
⑴ 区分番号「K514-3」,「K51
45 - 5」,「K552」,「K552-2」,「K674」,「K674-2」,「K675」の「2」
から「K675」の「5」まで,「K677」,「K677-2」,「K680」,「K684-2」,「K696」,「K705」,「K706」,
「K716-3」及び「K716-5」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は,2個を限
度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第2号)
第2 届出に関する手続き
第4 経過措置等
表2 施設基準の改正により,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定していた保険医
療機関であっても,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なも
の(抜粋)
医師事務作業補助体制加算(許可病床が全て一般病床である保険医療機関を除く。)
データ提出加算
精神科救急入院料(令和2年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
精神科急性期治療病棟入院料(令和2年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
精神科救急・合併症入院料(令和2年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
表3 施設基準等の名称が変更されたが,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定して
いた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
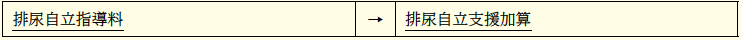
初・再診料の施設基準等
第2の6 オンライン診療料
1 オンライン診療料に関する施設基準
⑵ 当該保険医療機関内に脳神経外科
若しくは又は脳神経内科の経験を5年以上有する医師又
は頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置しているこ
と(頭痛患者に対して情報通信機器を用いた診療を行う場合に限る。)。
入院基本料等加算の施設基準等
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等
⑸ 内科,精神科,小児科,外科,整形外科,脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し,当
該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし,
地域において質
の高い医療の提供体制を確保する観点から,医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ
とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り,小児科,産科又は産婦人科の標
榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても,施設基準を満たし
ているものとする。なお,精神科については,24 時間対応できる体制(自院又は他院の精
神科医が,速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば,必ずしも標榜し,入院医療
を行う体制を必要としないものであるが,この場合であっても,以下のいずれも満たすもの
であること。
ア・イ (略)
3 総合入院体制加算3に関する施設基準等
⑶ 上記と同様の訂正
第4の4 看護職員夜間配置加算
1 看護職員夜間12 対1配置加算1の施設基準
⑻ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち,4
項目以上を満たしていること。ただし,当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2
交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は,ア及びウからコまでの
うち,4項目以上を満たしていること。なお,各項目の留意点については,別添3の第4の
3の9の⑶と同様であること。
アからクまで (略)
ケ 当該保険医療機関において,夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所
を設置してお
り,夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。を設置している
こと。
コ (略)
第14 緩和ケア診療加算
1 緩和ケア診療加算に関する施設基準
⑸ ⑴のア
,及びイ
,オ及びカに掲げる医師のうち,悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る
診療を行う場合には,以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また,
末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には,ア,イ又はウのいず
れかの研修を修了している者であること。なお,後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
アからウまで (略)
⑻ ⑴のア
,及びイ
,オ及びカに掲げる医師については,緩和ケア病棟入院料の届出に係る担
当医師と兼任ではないこと。ただし,緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名で
ある場合は,緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については,緩和ケア病棟入
院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
第21 感染防止対策加算
1 感染防止対策加算1の施設基準
⑻ ⑺に規定するカンファレンスは,⑵のアからエ及び2の⑶のアからエの構成員それぞれ1
名以上が直接対面し,実施することが原則であるが,以下のアからウを満たす場合は,リア
ルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機
器を用いて
実施参加することができる。
アからウまで (略)
⑼ 当該保険医療機関又は感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関が「別添3」の「別
紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機
能病院,許可病床数が400 床以上の病院,DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届
出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)の場合は,以下のア及び
イを満たすとき
はに限り,ビデオ通話が可能な機器を用いて
実施参加することができる。
ア・イ (略)
2 感染防止対策加算2の施設基準
⑻および⑼ 上記と同様の訂正
4 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
⑷ 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。
ア (略)
イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて,アで設定した対象患者を把握後,適切な微生
物検査・血液検査・画像検査等の実施状況,初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性,
必要に応じた治療薬物モニタリングの実施,微生物検査等の治療方針への活用状況などを
経時的に評価し,必要に応じて主治医にフィードバックを行い,その旨を診療録等に記載
する。
第26 の2 後発医薬品使用体制加算
2 届出に関する事項
後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は,別添7の様式40 の3を用いること。
なお,
当該加算の届出については実績を要しない
第26 の4 データ提出加算
4 届出に関する事項
⑹ 基本診療料の施設基準等第十一の
十一九に掲げる,データ提出加算の届出を行うことが困
難であることについて正当な理由がある場合とは,電子カルテシステムを導入していない場
合や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技
術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
特定入院料の施設基準等
第11 回復期リハビリテーション病棟入院料
1 通則
⑹
2の⑷及び⑸又は3の⑸において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては,当
該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価については,別添6の別紙21 を用いて測定すること。(以下略)
⑺
2の⑷及び⑸又は3の⑸において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては,毎
年7月において,1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入
院していた患者の日常生活機能評価について,別添7の様式49 の4により地方厚生(支)
局長に報告を行うこと。(以下略)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第3号)
第2 届出に関する手続き
4 届出に当たっては,当該届出に係る基準について,特に定めがある場合を除き,実績期間を
要しない。
⑶ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料,長期脳波ビデオ同時記録検査1,光トポグラフィー,
終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外の場合)(安全精度管理下で行うもの),筋電図検査(単
線維筋電図(一連につき)),骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術),
後縦
靱帯骨化症手術(前方進入によるもの),脳腫瘍覚醒下マッピング加算,網膜付着組織を含
む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの),人工中耳植込術,人工内耳植込術,植込型骨
導補聴器移植術,植込型骨導補聴器交換術,鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術
を含む。),鏡視下喉頭悪性腫瘍手術,
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を
伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)),胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内
視鏡手術用支援機器を用いる場合),(中略)腹腔鏡下仙骨腟固定術,腹腔鏡下仙骨腟固定術
(内視鏡手術用支援機器を用い
るた場合),腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器
を用いる場合),腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。),腹腔鏡下子宮悪性腫瘍
手術(子宮頸がんに限る。),腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用
支援機器を用いる場合),高エネルギー放射線治療,1回線量増加加算
,並びに強度変調放
射線治療(IMRT)
,腎代替療法指導管理料並びに導入期加算1及び2に係る年間実施件数
第4 経過措置等
表1 新たに施設基準が創設されたことにより,令和2年4月以降において当該点数を算定する
に当たり届出の必要なもの(抜粋)
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算1
子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する
子宮附属器腫瘍摘出術乳房切
除術に限る。)
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合)
表2 施設基準の改正により,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定していた保険医
療機関及び保険薬局であっても,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届
出の必要なもの(抜粋)
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用
いる場合)
調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で,
令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
表3 施設基準等の名称が変更されたが,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定して
いた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
第1の6 外来栄養食事指導料
1 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
⑴ 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適し
たリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し,
外来化学療法を実施してい
る保険医療機関に5年以上勤務し,栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る
3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。
第4 糖尿病合併症管理料
2 届出に関する事項
糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は,別添2の
2様式5を用いること。
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
2 届出に関する事項
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は,別添2の
2様式5の2を用いること。
第4の8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
2 届出に関する事項
乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準に係る届出は,別添2の
2様式5の9を用いるこ
と。
第4の10 腎代替療法指導管理料
1 腎代替療法指導管理料に関する施設基準
⑴ 以下の要件を満たしていること。
ア・イ(略)
ウ 腎移植について,患者の希望に応じて適切に相談に応じており,かつ,腎移植に向けた
手続きを行った患者が前年度に3人以上いること。なお,腎移植に向けた手続き等を行っ
た患者とは,臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者,先行
的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
第8 開放型病院共同指導料
1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
⑵ 次のア又はイのいずれかに該当していること。
ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)
1020 以上の
診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師
の5割以上が登録していること。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する,当該病院の開設者と関係のない(雇
用関係のない)
105以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地
域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には,
当該診療科の医師が常時勤務していること。(なお,医師が24 時間,365 日勤務すること
が必要であり,医師の宅直は認めない。)
第11 の5 肝炎インターフェロン治療計画料
1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
⑴ 肝疾患に関する専門的な知識を持つ
常勤の医師による診断(活動度及び病期を含む。)と
治療方針の決定が行われていること。
第16 の11 持続血糖測定器加算
1 持続血糖測定器加算に関する施設基準
⑵ 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し,専門の知識及び5年以上の経験を有
し,持続血糖測定器に係る適
切な研修を修了したする常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
ウ 糖尿病の治療に関し,持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し,持
続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されて
いること。
なお,ここでいう適切な研修とは,次の事項に該当する研修のことをいう。
エ ア及びウに掲げる適切な研修とは,次の事項に該当する研修のことをいう。
イ 医療関係団体が主催する研修であること。
ロ 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識,評価方法,セルフケア支援,持続血
糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであるこ
と。
第18 の1の2 遺伝学的検査
1 遺伝学的検査の施設基準の対象疾患
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(
令和2年平成30 年3
月5日保医発0305 第1号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第3部第1
節第1款D006-4遺伝学的検査⑴のエ
又はオに掲げる疾患
第22 の3 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
2 届出に関する事項
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストの施設基準に係る届出については,別添2
の様式24 の6
及び様式52 を用いること。
第22 の4 胎児心エコー法
2 届出に関する事項
胎児心エコー法の施設基準に係る届出については,別添2の様式24 の3
及び様式52 を用い
ること。
第22 の5 ヘッドアップティルト試験
2 届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については,別添2の様式24 の7
及び様
式52 を用いること。
第26 の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー
1 安全精度管理下で行うものに関する施設基準
⑶ 終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の場合を年間50 症例以上及び反復睡眠潜
時試験(MSLT)
検査を年間5件以上実施していること。
2 届出に関する事項
終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は,別添2の様
式27 の2の2
及び様式52 を用いること。
第35 の2 血流予備量比コンピューター断層撮影
2 届出に関する事項
血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準に係る届出は,別添2の様式37 の2及び
様式52 を用いること。
第38 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)
3 届出に関する事項
⑶ 当該治療が行われる専用の機能訓練室の
配置図及び平面図を添付すること。
第46 難病患者リハビリテーション料,第47 の2 がん患者リハビリテーション料,第47 の3
認知症患者リハビリテーション料
2 届出に関する事項
⑶ 当該治療が行われる専用の機能訓練室の
配置図及び平面図を添付すること。
第49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」「小規模なもの」
2 届出に関する事項
⑶ 当該治療が行われる専用の施設の
配置図及び平面図を添付すること。
第55 の2 精神科在宅患者支援管理料
3 届出に関する事項
⑵ 精神科在宅患者支援管理料「3」の施設基準に係る届出は別添2
の-2を用いること。
第57 の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準
⑵ 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア・イ (略)v
ウ 腎移植について,患者の希望に応じて適切に相談に応じており,かつ,腎移植に向けた
手続きを行った患者が前年度に3人以上いること。なお,腎移植に向けた手続き
等を行っ
た患者とは,臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者,先行
的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
第57 の8 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
2 届出に関する事項
⑴ 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係
る届出は,別添2の様式50 の4及び様式52 を用いること。
⑵ 当該治療に従事する医師の氏名,勤務の態様(常勤・非常勤,専従・非専従,専任・非専
任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第61 の2の2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
2 届出に関する事項
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に係る届出は,別添2の様式別添
56 の7及び様式52 を用いること。
第61 の7 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を
用いる場合)
1 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる
場合)の施設基準
⑴ 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
⑵ 以下のアからエまでの手術を術者として,合わせて
510 例以上実施した経験を有する常
勤の医師が1名以上配置されていること。
ア 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
ウ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内
視鏡手術用支援機器を用いる場合)
エ 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
⑶から⑼まで(略)
第75 の4 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
3 届出に関する事項
⑶ 外科又は消化器外科を担当する医師の氏名,勤務の態様(常勤・非常勤,専従・非専従,専任・
非専任の別)及び勤務時間を,別添2の様式4により提出すること。
第76 の2 同種死体膵島移植術
1 同種死体膵島移植術に関する施設基準
⑴〜⑶ (略)
⑷ 同種死体膵島移植術を行うに当たり医療関係団体より認定された施設であること。
(
54) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用
に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出てい
ること。
(
65) 同種死体膵島移植術の実施に当たり,再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条
に規定する再生医療等提供基準を遵守していること。
2 届出に関する事項
⑴ 同種死体膵島移植術の施設基準に係る届出は,別添2の様式52 及び様式57 の2を用いる
こと。v
⑵
医療関係団体関連学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付するこ
と。
⑶ (略)
第77 の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術,腹腔鏡下小切開腎摘出術,腹腔鏡下小切開腎(尿管)
悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開腎部分切除術,腹腔鏡下小切開腎摘出術,腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍
手術の施設基準及び届出に関する事項は,第72 の4
の2腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清
術の例による。
第77 の6 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は,第72 の4
の2腹
腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
第77 の8 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は,第72 の4
の2腹
腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
第78 の2 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第72 の4
の2腹腔鏡
下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
第78 の4 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
2 届出に関する事項
⑴ 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準に係る届出は,別添2の様式52 及び様
式71 の3を用いること。
⑵ 医師が経験した当該手術の症例数が分かる書類を添付すること。
(2
3) 倫理委員会の開催要綱(運営規定等)の写しを添付すること。
厚生労働省告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
B001 特定疾患治療管理料
12 心臓ペースメーカー指導管理料
注5 ロ又はハを算定する患者について,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において,前回受診月の翌月から今回受診月の
前月前日までの期間,遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は,遠隔モニ
タリング加算として,それぞれ260 点又は480 点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限
り,11 月を限度とする。)を乗じて得た点数を,所定点数に加算する。
第8部 精神科専門療法
第1節 精神科専門療法料
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
注8 1を算定する患者であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において,
当該保険医療機関における直近の入院にお
いて,区分番号B015 に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して,精神科を
担当する医師の指示の下,保健師,看護師又は精神保健福祉士が,療養生活環境を整備するた
めの指導を行った場合に,療養生活環境整備指導加算として,初回算定日の属する月から起算
して1年を限度として,月1回に限り250 点を所定点数に加算する。
第9部 処置
J044 救命のための気管内挿管
500480 点
J044-2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日につき)
480400 点
特掲診療料の施設基準等
別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
一
がん患者であって,がんの治療のために入院している間に手術,化学療法(骨髄抑制が見込ま
れるものに限る),放射線治療若しくは造血幹細胞移植食道がん,肺がん,縦隔腫瘍,胃がん,
肝臓がん,胆嚢がん,大腸がん又は膵臓がんと診断された患者であって,これらのがんの治療の
ために入院している間に閉鎖循環式全身麻酔による手術が行われる予定のもの又は行われたもの
二 舌がん,口腔がん,咽頭がん,喉頭がんその他頚部リンパ節郭清を必要とするがんと診断され
た患者であって,これらのがんの治療のために入院している間に放射線治療若しくは閉鎖循環式
全身麻酔による手術が行われる予定のもの又は行われたもの
三 乳がんと診断された患者であって,乳がんの治療のために入院している間にリンパ節郭清を伴
う乳腺悪性腫瘍手術が行われる予定のもの又は行われたもの
四 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移と診断された患者であって,これらのがんの治療のために入院し
ている間にこれらの部位に対する手術,化学療法若しくは放射線治療が行われる予定のもの又は
行われたもの
五 原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍と診断された患者であって,これらのがんの治療のために入院
している間に手術若しくは放射線治療が行われる予定のもの又は行われたもの
六 血液腫瘍と診断された患者であって,血液腫瘍の治療のために入院している間に化学療法若し
くは造血幹細胞移植が行われる予定のもの又は行われたもの
七 がんと診断された患者であって,がんの治療のために入院している間に化学療法(骨髄抑制が
見込まれるものに限る。)が行われる予定のもの又は行われたもの
二八 緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって,症状の増悪
により入院している間に在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要なもの